複利(複利効果)とは
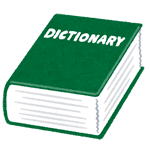
複利(ふくり:Compound Interest)とは、元金に再投資された利息分を加えたものに付く利息のこと。例えば、1年複利の場合は金利計算が年に一回おこなわれ、翌1年後には、当初の元金に対して1年前に付与された金利分に対しても利子が付く。 いわゆる「雪だるま式」とも呼ばれ、利息に対して利息が付いていくことで加速度的に資産(負債)が増加することを複利効果と呼ぶ。 複利という考え方は資産運用など様々な運用で重要な考え方である。例えば、100万円の元金を30年間金利5%で運用した場合、単利と複利(1年複利とする)では以下のように運用成績が異なる。 単利の場合 複利の場合 複利効果は利回り(利息・利子)が大きいほど、運用期間が長くなるほどその効果は大きくなっていく。資産運用においては利回りと時間が大切であるといわれるのはこの複利効果から導き出されている。 一方で、複利効果は負の側面で働くこともある。代表的なのが借金に対する複利効果である。通常多くの借入金(キャッシングやローン、住宅ローンなど)も基本的に複利となる。こちらも借入利息と借入期間が長いほど総返済額は大きくなる。
計算は単純でこの72を「任意の数字」で割ったときに示される「答え」のうち、「任意の数字=利率」、「答え=必要な年数」となる。例えば、利率4%で資産運用をする場合、72/4=18年、つまり、毎年4%で運用したら18年かけて資産が2倍になるというものである。 |
|
もしかして?(複利(複利効果)関連用語一覧)
|
複利(複利効果)の登録カテゴリ情報
| メインカテゴリ:ふ行 |
| サブカテゴリ(3):ジャンル別 , 金利 , 索引別 |
なお、「金融経済用語辞典トップページ」からも情報をお探しいただけます。
複利(複利効果)に関するクチコミ・投稿情報
複利(複利効果)に関連すると考えられるクチコミや投稿情報を表示しています。できる限り複利(複利効果)に合った情報を表示できるよう努力しておりますが、時事的な質問などが表示されたり、不適切な情報が掲載される可能性もありますが、ご了承ください。
見つかりませんでした